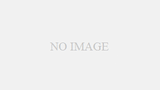1. 基礎知識(定義・概要)
「めまい」とは、自分や周囲が動いていないのに動いているように感じる異常感覚を指します。
大きくは次の3つに分類されます。
回転性めまい:自分や周囲がぐるぐる回る(内耳・前庭障害が多い)
浮動性・動揺性めまい:ふらつき・ふわふわする(中枢性・自律神経・循環系)
失神性めまい:意識が遠のく感じ(循環器・血圧・自律神経系)
2. 主な原因と特徴
| 分類 | 主な疾患・機序 | 特徴 |
|---|---|---|
| 末梢性めまい | 良性発作性頭位めまい症(BPPV)、メニエール病、前庭神経炎、中耳炎など | 回転性が多く、耳鳴り・難聴を伴うことあり |
| 中枢性めまい | 脳幹・小脳梗塞、出血、腫瘍など | 持続性・激しい・神経症状を伴う |
| 循環・自律神経性 | 起立性低血圧、ストレス、貧血など | フワフワ、立ちくらみ感、意識遠のく感じ |
| 頸性めまい | 頸椎の可動制限・血流障害・筋緊張 | 頸部運動で誘発されやすく、肩こり・頭重感を伴う |
3. 発生メカニズム(簡易まとめ)
内耳・前庭由来:三半規管・耳石器の障害により平衡感覚が乱れる
中枢由来:脳幹や小脳の血流障害による平衡系の情報統合不全
頸性要因:頸椎の姿勢不良・筋緊張・椎骨動脈血流低下による平衡入力異常
自律神経性:ストレスや睡眠不足による交感神経過活動、循環不全
4. 問診で確認すべきポイント
発症状況(急か徐々に/起床時・寝返り時・立ち上がり時など)
めまいの性状(回転/ふわふわ/立ちくらみ)
持続時間(数秒~数日)
誘発動作(頭を動かす/寝返り/頸部回旋)
付随症状(耳鳴り、難聴、吐き気、視覚異常、しびれ)
既往(高血圧・糖尿病・心疾患・頸椎疾患・耳疾患)
薬歴・ストレス・睡眠・姿勢
5. 視診・触診・徒手検査のポイント
頸椎可動域の左右差・誘発性の有無
頸部筋群(斜角筋、胸鎖乳突筋、僧帽筋)の過緊張・圧痛
頭部回旋での眼振確認(簡易Dix-Hallpike法)
立位・閉眼時のバランス(ロンベルグ徴候)
血圧・脈拍(起立性低血圧が疑われる場合)
6. 鑑別フローチャート(臨床用)主訴:めまい ↓ A. 「突然の激しい回転」「言語障害」「手足のしびれ・脱力」→ 中枢性疑い → 緊急紹介 ↓ B. 「耳鳴り・難聴・耳閉感」→ メニエール病 or 内耳性めまい ↓ C. 「寝返り・頭位で誘発」「数秒〜1分で軽快」→ 良性発作性頭位めまい症(BPPV) ↓ D. 「頸部運動で増悪」「肩こり・後頭部重だるさ」→ 頸性めまい ↓ E. 「起立・立ち上がりでふらつく」「倦怠感・貧血」→ 循環性/自律神経性 ↓ F. 各種スクリーニングで原因特定 → 機能的改善・指導へ
7. 施術アプローチ(整骨院での対応)
1. 頸性めまい・筋緊張型への対応
頸椎~上部胸椎のモビライゼーション(過度な矯正は避ける)
胸鎖乳突筋・斜角筋・後頭下筋群のリリース
肩甲帯可動性の改善、呼吸筋調整
姿勢・頭部前方位の修正指導
自律神経の安定(軽い頭蓋リリース・深呼吸訓練)
2. 自律神経性・循環性めまいへの対応
首・胸郭・横隔膜の動き改善(呼吸筋調整)
軽運動・ストレッチ・温熱療法で末梢循環促進
睡眠・栄養・水分・ストレス管理の指導
過呼吸傾向への呼吸再教育
3. BPPVへの注意
自行施術は禁忌。必要に応じ耳鼻科紹介。
発作期は安静。動作誘発しないように指導。
8. 自宅でのセルフケア・生活指導
十分な睡眠・水分補給を心がける
ストレス・過労・長時間の同姿勢を避ける
頸部ストレッチ(ゆっくり、痛みのない範囲で)
立ち上がる時は数秒静止してから動く(起立性低血圧対策)
目を閉じず焦点を合わせて安定感を保つ練習
めまい日誌で発作時の状況・誘因を記録
9. 速やかに医療機関紹介すべきサイン
突然の激しい回転性めまいに加え、
言語障害、手足の麻痺、しびれ、歩行困難がある
めまいが数時間以上持続し改善しない
耳鳴り・難聴・耳漏・発熱などが悪化傾向
意識障害・頭痛・嘔吐を伴う
高血圧・糖尿病など既往のある高齢者
10. 臨床ポイントまとめ
めまいは「耳」「脳」「首」「血圧」「自律神経」いずれかが関与。
最初に「危険な中枢性」を見逃さないこと。
頸性めまいは整骨院でも機能改善が期待できる領域。
姿勢・呼吸・筋緊張・ストレス管理が治療の中核。
改善が乏しい、悪化傾向がある場合は速やかに医師へ連携。
11. 患者への説明例
「めまいには耳の中の平衡器が関係するもの、脳や首、血圧の変化によるものがあります。
あなたのめまいは首の緊張や姿勢の影響を受けている可能性がありますので、
首と肩の動きを整え、血流と自律神経のバランスを改善していきましょう。
ただし、強い吐き気や手足のしびれなどが出たらすぐ病院を受診してください。」