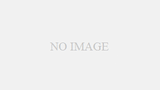1. 基礎知識(定義・概観)
頭痛は「外部に原因がないにもかかわらず本人に感じられる頭部の痛み」を総称します。大きくは
- 一次性頭痛(原因が頭自体の構造異常ではない:緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛 等)
- 二次性頭痛(他疾患が原因:出血、感染、腫瘍、頸椎病変、薬剤性 等)
に分けられます。一次性が大半ですが、二次性の見逃しは重大なので注意が必要です。
2. 主なタイプと特徴(簡潔)
- 緊張型頭痛:帯状の締めつけ感/首肩のコリと関連/比較的軽度〜中等度、慢性化しやすい。
- 片頭痛:片側性で拍動性、悪心・光過敏・音過敏を伴うことあり。女性に多く、誘因(ホルモン・食事・睡眠不規則)が明確なことが多い。
- 群発頭痛:極めて激烈な片側眼周囲痛、発作性に集中的に出現。自発的眼充血や流涙を伴うことが多い。
- 頸性(頸椎由来)頭痛:頸部の運動や姿勢で増悪。後頭部〜側頭部に放散することあり。
- 二次性頭痛:急激で今まで経験したことのない激痛、神経学的症状、発熱などがあれば医療機関精査。
3. 発生メカニズム(概説)
- 緊張型:頸肩部筋の過緊張→筋・筋膜トリガー→周辺血流低下・神経感作
- 片頭痛:中枢および血管系の感作/セロトニン等の神経伝達物質変動→三叉神経血管複合体の活性化
- 群発:視床下部の機能性変化+三叉神経血管の反応性(季節性・睡眠リズムに関連)
- 頸性:頸椎構造・関節・筋の障害が頭痛閾値を下げる
4. 問診で必ず確認するポイント
- 痛みの性状(拍動性・締めつけ・刺すような等)
- 発症様式(突発か徐々か、持続時間、周期性)
- 位置(片側/両側、前頭/側頭/後頭)
- 誘因(睡眠不足、食事、アルコール、ストレス、月経)
- 合併症状(悪心・嘔吐・光過敏・音過敏・めまい・神経学的症状)
- 既往・薬・最近の外傷や感染(耳鼻科系、歯科治療など)
- 頻度・日常生活への影響(仕事欠勤や家事不能など)
5. 視診・触診・徒手検査で見る点
- 頭頸部姿勢(頭部前方位、肩の高さ、胸郭の動き)
- 頸部可動域(特に回旋・伸展で誘発されるか)
- 頸〜肩〜こめかみ〜側頭部の圧痛点(トリガーポイント)
- 顎関節の状態(顎関節症は頭痛誘因)
- 神経学的簡易チェック(意識レベル・言語・片麻痺・瞳孔差などの有無)
※神経学的異常があれば速やかに医療機関へ
6. 鑑別のフローチャート(臨床用・短縮版)
主訴:頭痛
↓
A. 「急性で今までにない激痛」「意識障害」「神経症状」「発熱」「嘔吐」→ 二次性疑い → 緊急医療機関紹介
↓
B. 反復性・既往あり → 詳細問診
↓
1) 拍動性で悪心・光過敏あり → 片頭痛候補
2) 帯状の締め付け感、首肩のコリ強い → 緊張型候補(頸性含む)
3) 極度の片側眼周囲痛+自律症状 → 群発頭痛候補
4) 頸部動作で誘発 → 頸性頭痛
↓
C. 機能的因子(姿勢・睡眠・ストレス)評価 → 治療方針へ
7. 治療アプローチ(整骨院での機能的対応)
(目的:誘因の除去・筋・関節のバランス回復・自律神経安定化)
急性増悪時の原則
- 強い刺激は避ける(過度の圧迫や強い矯正は悪化の原因に)
- 痛みによる不安を軽減し、安静と呼吸を促す
具体的施術例
- 頸部・肩甲帯・胸椎のモビライゼーション(可動性改善)
- 後頭下筋群/胸鎖乳突筋/僧帽筋上部/肩甲挙筋の筋膜リリース/トリガーポイント療法
- 顎関節の評価・必要なら軽いリリース(顎関節症が併存する場合)
- 呼吸訓練(横隔膜機能改善)・副交感優位への誘導(軽度の自律神経調整)
- 神経感作が疑われる場合は漸進的な運動負荷療法と認知的アプローチの併用
- 片頭痛には発作期の安静+暗所での休養を支持、反復発作には生活習慣指導(睡眠・食事・トリガー回避)
徒手療法以外の介入
- 指導:休息方法・睡眠衛生・水分補給・カフェイン/アルコール管理
- 自主訓練:首肩ストレッチ、肩甲帯エクササイズ、姿勢改善エクササイズ
- 必要時、医師受診を促す(薬物療法や専門的検査の検討)
8. 自宅でできるセルフケア(患者指導)
- 定期的な休憩(PC作業は60分毎に1回立ち上がる)
- 温熱療法:筋緊張が強い部位は温めて緩和(緊張型に有効)
- 冷却:片頭痛の発作初期は冷却で軽減することがある
- 深呼吸(横隔膜呼吸)で自律神経を整える
- 睡眠ルーティンの確立、規則正しい生活リズム
- トリガー日誌:食事・睡眠・天候・女性の月経周期・アルコール等を記録し誘因を把握
9. 紹介基準(速やかに医師へ)
- 「今までにない突然の激しい頭痛(“雷鳴のよう”)」
- 意識障害、言語障害、片麻痺、視野欠損などの神経学的症状
- 新たに出現した長引く高熱を伴う頭痛
- 頭部外傷後の頭痛(特に意識消失・嘔吐を伴うもの)
- 耐えがたい嘔吐・首の硬直(髄膜刺激症状)
- 持続する・急速悪化する視力障害や運動障害
- 薬剤の過剰使用が疑われる頭痛(反跳性頭痛)
これらがあれば速やかに救急受診や専門医受診を勧めてください。
10. 臨床でのチェックリスト(簡易)
- 頭痛の性状(拍動性/締め付け/刺すよう)
- 発作の持続時間・頻度・日常生活影響度
- 合併症状(悪心・嘔吐・めまい・麻痺)
- 頸肩部のトリガーポイント有無
- 睡眠・ストレス・薬剤歴の確認
- 紹介基準に該当するかどうか
11. 患者への説明例(分かりやすく)
- 「頭痛にはいくつかタイプがあり、筋肉のコリが原因のもの、血管や神経の働きが関係するもの、他の重大な病気が原因のものがあります。あなたの頭痛は(緊張型/片頭痛/頸性など)に近いので、まずは筋緊張を取る、姿勢を整える、生活習慣を見直すことから始めましょう。もし赤いサイン(急な激痛や麻痺など)が出たらすぐに病院へ行きましょう。」
12. まとめ(臨床ポイント)
- 一次性頭痛が多いが、二次性頭痛の除外が最重要。
- 整骨院では「筋・関節・姿勢・自律神経」に対する機能的アプローチで改善を図る。
- 患者教育(トリガー回避・睡眠・ストレス管理)が治療の半分を占める。
- 改善しない、あるいは悪化する場合は速やかに医療機関へ連携する。